手紙が大事だった時代を描いた『チャーリングクロス街84番地』
『チャーリングクロス街84番地』という映画を見ました。どうしてなのかわからないけれど、Netflixを開いたら、自然にこの映画が目について、気がついたときには見入っていました。(ネタバレありなのでご注意を)
記憶に間違いがなければ、1980年代に、たぶん封切り上映ではなく、二番館のようなところで見たように記憶しています。古書店の話でアンソニー・ホプキンスが出ていたというのをうっすら記憶していただけだったので、ほぼ新たに見るような新鮮な気持ちで見ることができました。
ストーリーはシンプル。第二次世界大戦後の1950年代、英文学をこの上なく愛するニューヨーク在住の作家へレーヌと、彼女が探していた英文学の本、とりわけ美しい装幀で学術的に価値のある書籍を見つけ出しては提供することになるロンドンのマークス古書店の店主フランクとの、20年以上にも渡る手紙でのやり取りを軸に、マークス古書店の社員やフランクの家族、へレーヌの友人たち、周囲の人々との心温まる交流を描いた物語です。
ふたりのやり取りは手紙やたまに贈りあう贈り物だけで、ついには一度も直接会うことはなかったのですが、文学を、本を愛するという点で、理解し合っていたふたりの大西洋を越えた友情が丁寧に描かれていました。
主人公が原作者のリアルストーリー
へレーヌをアン・バンクロフト(=「奇跡の人」のアン・サリヴァンや「卒業」のミセス・ロビンソン役)が演じ、英国紳士の古書店主フランクをアンソニー・ホプキンス、フランクの妻をジュディ・デンチが演じています。原作は主人公のへレーヌのモデルとなった実在の作家ヘレン・ハンフが書いた「チャリング・クロス街84番地」(中公文庫)。いまや電話やメールどころか、SNSのメッセージで世界中の誰とでもリアルタイムでやり取りができる時代ですが、手紙がコミュニケーションの中心だったのはわずかに50年前。僕はぎりぎりそういう時代を知っている世代。思えば世界は随分と狭くなってしまったのかもしれません。
1950年代はまだまだ大西洋を飛行機で越えることは可能でも、金銭的には気軽にできないのが現実でした。劇中でも、へレーヌがロンドンへ行って、フランクに会いたいと願っても、現実的には叶わなかったそういう時代でした。いまや誰もが世界のどこに行くのもちょっとの努力で叶うようになっていて、もうすでに彼らの海を越えた手紙の重さは、いまの時代を生きる僕たちには、リアルには感じられないかもしれません。
古き良き書店はファンタジーになったのか?
先日、Twitterで書店員の方が客にある分野の関連書籍を探してほしいと言われ、「レファレンスは本屋の仕事ではないので、探してほしければ図書館に行って欲しい」といった主旨の投稿をしていて驚きました。自分の担当分野の関連書を探すことなど、業務の中では当たり前だったので(僕は元書店員です)、正直、その投稿には反対意見もあるだろうと思っていたのですが、驚くことにこれに同意して、聞いてきた客を非常識とまで言う現役の書店員がいて更に驚きました。たしかにいまや書店がレファレンスの機能を持つなど、それこそ非常識なのかもしれませんが、正直、驚きを越えて、悲しみすら覚えました。いまの書店員にとっては、へレーヌもフランクも、もうファンタジーの世界の住人なのかも知れません。
現実には難しくとも、書店とはそういう存在だったことを、この映画を通じて知ってもらえたら、と思いました。
『チャーリングクロス街84番地』
https://www.netflix.com/title/60023132
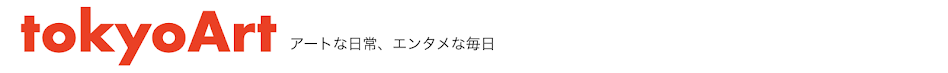


1 件のコメント:
uns98m02w
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
コメントを投稿