バンドの屋台骨であるドラマーで、それもプロであったとしても、音楽をやる以上、楽しまなきゃと思うのです。そういう意味ではエンディングのニーマンとフレッチャーの鬼気迫るセッションはおもしろい演出だとは思うんだけど、そこから楽しさが伝わるのか、というとそうでもない。
ジャズのセッションの醍醐味って、本当にプロ中のプロのプレイヤー同士が繰り出す、テクニックだけでは表現できないグルーブがその場に生まれてこそ、感じられるもので、やはりそこにはプレイヤー同士の信頼関係(それは対立する緊張感も含め)があるから生まれるのであって、あの場のニーマンとフレッチャーはそんな感じだったんでしょうか?
二人の間に旧敵同士に生まれる一種の共有感覚とか連帯感のようなものがあった(とする脚本だった)のかもしれないけど、そこまでのストーリーでの二人の経緯を考えると、どう考えても「音楽が生まれる関係」ではないように思うのです。
そうやって見てくると、僕には、どうにもチャゼル監督は音楽の本質からあえて目を背けているような気さえするんだな、なんか。チャゼル監督にとってのフレッチャーに対して復讐でもしているような、そんな感じ。僕の思い違いだといいんだけど。それとも『ラ・ラ・ランド』では、音楽を違った描き方で表現しているんだろうか?
あ、そうそう。血まみれのスティックを象徴的に描いてるけど、そんなの普通だから。楽器やったことがある人なら、ドラムに限らず、みんな血まみれ。よく言うじゃん、血の滲む努力って、あれ、リアルだから。
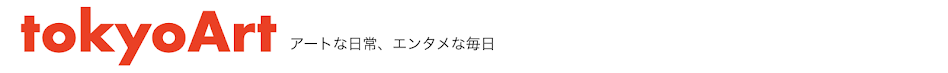

0 件のコメント:
コメントを投稿