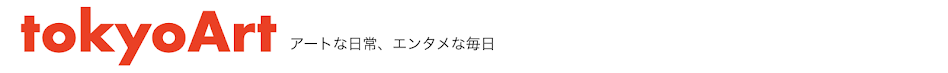|
りんご選定鋏(左)、僕もこどもの頃はよく食べていた「凍み餅」(中)
21_21 DESIGN SIGHTエントランスの「テマヒマ展」バナー(右) |
昨年7月、
21_21 DESIGN SIGHTでは東日本大震災を受け、
特別企画「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」を開催しました。東北の力を「衣」を通して見つめたすばらしい展覧会でした。今回、4月27日より行われている「テマヒマ展〈東北の食と住〉」は21_21 DESIGN SIGHTのディレクターを務めるグラフィックデザイナーの佐藤卓さんとプロダクトデザイナーの深澤直人さんの視点から、東北の「食」と「住」にフォーカスしたものです。
本展では「テマヒマ」をキーワードにしており、まさに労力(手間=テマ)と時間(暇=ヒマ)をかけて生み出す東北のものづくりへの姿勢を、映像と実物を展示して紹介しています。このテマヒマは東北で生活する者について回る長い冬という時間と、その中で素材を工夫して生み出す知恵と労力にあります。とりわけ食については、凶作とそれにともなう飢饉に見舞われていた東北では、備蓄や救荒食物*への知恵が備わってきました。かの米沢藩の名君、上杉鷹山は食用にできる草木や果実の特徴とその調理法を示した「かてもの」を編纂させるなど、庶民だけでなく東北に暮らすものにとって、テマヒマをかけるのは共通の認識であったと思います。
※救荒食物(きゅうこうしょくもつ):
飢饉や災害に備えて主食に変えて利用された食物や、備蓄できるように加工された代用食物。雑穀や葉や根、実、海藻などが用いられたが、とりわけ東北では寒さを利用してフリーズドライにしたものが多くみられる。
 |
| 「テマヒマ展」は六本木・東京ミッドタウンの21_21 DESIGN SIGHTで8月26日まで開催中です |
 |
| 地下ロビーには本展で紹介されている食や住に関連した品々と生産地が表示された東北6県の地図が |
会場では佐藤卓さんのグラフィックと深澤直人さんの空間構成、フードディレクターの奥村文絵さん、ジャーナリストの川上典李子さんらによって集められた東北の「食と住」にまつわる55種の品々を、トム・ヴィンセントさん、山中有さんによる撮りおろしの映像、西部裕介さんによる写真とともに紹介しています。
会場構成は映像で東北の食文化、住文化を紹介するギャラリー1と東北のものづくりの完成品、プロセス、材料や道具などの実物と写真を展示するギャラリー2で構成されています。とりわけ数々の実物が並べられたギャラリー2は、仙台出身の僕にとって、なにもかもが懐かしく親しみ深いものばかりで、ひととき時空を超えてこども時代に食べたり触ったりした故郷の品々に触れた思いをしました。
映像は7つのショートフィルムになっており、りんご箱を製作する作業場、きりたんぽを作る厨房、りんご剪定鋏を作る工房の様子などを捉えており、映像に合わせた音楽がより新鮮な映像作品になっていました。とりわけ、りんご箱の製作では、もとより小気味いい釘打ちのリズムに合わせて、ブラスハープの演奏が加わっており、僕の知るりんご箱製造の現場(製造現場に行った事はありませんが、学生時代に視聴覚教材で見た記憶があります)が、とてもスタイリッシュに見えました。まずここで7つの映像を見る事で、ギャラリー2にある実物展示がより興味深く見る事ができると思います。
 |
ギャラリー1では東北の食文化、住文化を映像的視点からとらえた
7つのショートフィルム「『テマヒマ展 〈東北の食と住〉』のための映像」
写真は「りんご剪定鋏(青森県弘前市)」 |
 |
| 東北の生産地に赴き捉えた写真の数々が展示されています。写真は「干し柿」 |
 |
| 会場には展示されている品々をモチーフにしたバナーが |
ギャラリー2の実物展示では、救荒食物と言われる保存食や地域に根ざした食品、東北の生活に不可欠な道具やそれらの道具から生み出された工芸品などが多く、いずれも種類多く並べられており、よくこれだけ集めたものだと正直驚きました。仙台出身とは言っても、やはり仙台は都会ですので、こうした素朴な食べ物や道具には僕の年代(1960〜1980年代を仙台で過ごしました)でもほとんど触れる事はありませんでしたが、「油麩」を切ったものが味噌汁に入っていたり、岩出山の「凍み豆腐」が煮物に入っているのはごく当たり前でした。ようやく生産者を見つけたという幻の「凍みイモ」はこどもの頃、粉にして餅のように食べさせられた記憶があります。実はいずれも育ち盛りだった時分の僕にとっては、あまりよい思い出ではないのですが…;;
 |
| いわなを焼いて乾燥させた久慈産の「綱干しいわな」 |
そうした僕ですら新鮮な驚きを持って見られる展示ですので、東北の独自の文化に触れた事のない方には大変珍しいものに写るのではないでしょうか? 東北を知るものにとっては懐かしさと親しみを、はじめて触れる方には驚きをもたらす展覧会ではないかと思います。また、こうした東北の知恵はこれまで通りの生活を見直す必要のあるこれからの日本(日本だけではないと思いますが)に暮らす人々にとって、なにかしら役立つ事は間違いないと思います。
 |
岩手県南部地方に伝わる幻の救荒食物のひとつ「凍みイモ」
粉にして湯で練って砂糖をまぶしてイモ餅はかなり小さな頃に食べた記憶があります |
 |
フランスパンのような長い麩は宮城県登米市の「油麩」
仙台でのこども時代にはこの油麩を切ったものが味噌汁の具に入ってました |
 |
駄菓子も実にたくさん展示されています
上は種類の多さは日本一の「仙台駄菓子」、下は諸越製の「きつね面」が珍しい「鶴岡駄菓子」 |
 |
どっしりとした重厚なつくりの天童の「柏戸イス」
山形県出身の関取、柏戸関の横綱昇進記念に贈呈されたのが名前の由来 |
 |
雪上作業用靴として天然生ゴムで手作りされた「ボッコ靴」
写真はかんじき装着用のリボンがついた短長タイプ |
 |
| テマヒマをかけるには職人の手が大事ですね |
 |
| 青森県弘前市の「りんご剪定鋏」の製作工程。剪定によってその年のりんごの味が決まるそうです |
 |
| 中庭には青森の「りんご箱」が高く積み上げられていますn |
 |
| 本展ディレクターのひとり。グラフィックデザイナーの佐藤卓さん |
本展の共同企画として東京ミッドタウンのとらやにおいて、東北産の原材料を用いて開発した新菓子とその開発の様子を収めた映像による「とらや×テマヒマ展」を同店店内のギャラリーにおいて開催しています。
今回、開発したのは、秋田県石孫本店の「寒仕込み 雪見蔵」の味噌に寒天を加えて固め、御前餡と岩手県産黒米を使った餅で包んだ『味噌黒米餅』、ずんだの原料である山形県産の裏漉しした「だだ茶豆」の枝豆に琥珀羹を加え、煉羊羹と重ねた『ずんだ羹』。いずれも各1個420円(税込)で同店で販売しています。
なお、販売期間はいずれも8月26日までですが、『ずんだ羹』は7月4日からの販売となります。本展会期中にとらや東京ミッドタウン店にて生菓子を購入すると本展入場料が200円割引(2名まで)に、また、入場券半券をとらや東京ミッドタウン店での会計時(1,500円以上)に提示するととらやオリジナルグッズがもらえます。
 |
| 『味噌黒米餅』。表面を少し焼くことで、香ばしさが引き立たっています |
[展覧会情報]
会期 :2012年4月27日(金)〜8月26日(日)
休館日 :毎週火曜日
開館時間:11:00〜20:00(入場は19:30まで)
会場 :21_21 DESIGN SIGHT(東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン・ガーデン内)
入場料 :一般1,000円、大学生800円、中高生500円、小学生以下無料
交通アクセス:
都営大江戸線・東京メトロ日比谷線「六本木」駅、千代田線「乃木坂」駅より徒歩5分
後援 :文化庁、経済産業省、
青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、港区
特別協賛:三井不動産株式会社
特別協力:株式会社 虎屋、株式会社 TOSEI
協力 :キヤノンマーケティングジャパン株式会社、マックスレイ株式会社
お問い合わせ:03-3475-2121
とらやの商品に関するお問い合せ:とらや東京ミッドタウン店 03-5413-3541