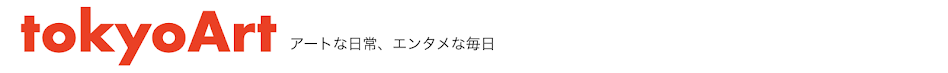メディアアーティストの八谷和彦さんが長年、続けているプロジェクト「オープンスカイ」。いわゆるメーヴェを現実のものとして、大空を翔けるプロジェクトです。メーヴェという名前は知らなくとも、『風の谷のナウシカ』でナウシカが操る一人乗りのグライダーといえば、知らない方はいないでしょう。
このプロジェクトのひとつのゴールとも言える、ジェットエンジンを搭載した実機での公開フライトが、2016年7月31日に北海道滝川市のたきかわスカイパークで行われました。10年以上にわたって進められてきたプロジェクトで、途中休止期間があったり、エンジンの調達が難しくなったり、紆余曲折を経て、満を持してのフライトだっただけに、僕も北海道まで行って、その勇姿をこの目でみたかったです。
僕が八谷さんのこの「オープンスカイ」にはじめてふれたのは、2003年の利根川河川敷での[1/2モデル]のラジコン機の飛行でした。当時はなんだかひさびさにアートに触れたくなっていた時期で、たまたまこの実験飛行のことを知って、うちからチャリで行ったものの(利根川はうちから車で10分ほど)、すでに実験は終わっていました。
それから数年経って、初の実物大の滑空機である[M-01]が製作され「愛・地球博」で展示されましたが、これにも残念ながら行けず、その翌年2006年にICCで開催された「オープンスカイ2.0」でようやく実機(?)に触れることができました。この時は取材でもなんでもなく、普通に展覧会を見に行ったのですが、なぜか写真を撮っていました。
 |
| こんな感じで実際に乗った気分が味わえました。「オープンスカイ2.0」(2006年/ICC) |
その後、二機目の滑空機として製作された[M-02]は実際にパイロットである八谷さんが搭乗して、飛行する実験が行われました。この時はまだ動力は搭載せず、ゴム索発航(人が引っ張って、ゴムパッチン方式で飛ばします)で飛ばしていました。
2008年に行われた「金沢アートプラットフォーム2008」において、「オープンスカイ」展示が行われ、金沢市内の公園でテストフライトが行われました。この時、取材に行っていた僕も、引っ張り要員に加えていただき、実際に飛び上がって、着地するのを目の前で見ることができました。
 |
| 離陸から着地まで撮影。「金沢アートプラットフォーム2008」(2008年) |
 |
| フライトを終えた八谷さん。「金沢アートプラットフォーム2008」(2008年) |
その後、実際にジェットエンジンを積んで空飛ぶ姿を心待ちにしていましたが、2010年にエンジンを搭載した[M-02J]の滑走試験の際にエンジントラブルの発生があり、約2年のプロジェクト休止を余儀なくされました。その後、機体改造、エンジン換装が行われ、2012年に野田スポーツ公園での滑走実験が行われ、2013年にはついに国土交通省航空局から試験飛行許可がおり、ジャンプ飛行が行われました。
いよいよジェットエンジンでの飛行を目前に、2013年にはアーツ千代田3331で「OPENSKY 3.0」が行われ、[M-02J]をはじめ、プロジェクトで製作されたすべての実験機やフライトシュミレータなどが展示されました。レッドブル・エアレースで知られるエアロバティックを知ったのは、この時でした。
 |
M-02Jを前に熱心に説明する八谷さん。「OPENSKY 3.0」(2013年/アーツ千代田3331)
|
 |
| ジェットエンジンを搭載したM-02J。「OPENSKY 3.0」(2013年/アーツ千代田3331) |
 |
| ジェットエンジンがおさまってます。「OPENSKY 3.0」(2013年/アーツ千代田3331) |
 |
| 忘れがちなのですが、アートプロジェクトなので、パイロットのユニフォームやヘルメットを含め、 トータルでデザインされています。「OPENSKY 3.0」(2013年/アーツ千代田3331) |
その後のテストフライトは北海道滝川市のたきかわスカイパークで継続されており、気軽に取材に行けなくなりましたが、2014年の公開試験飛行、そして今回の公開飛行などに常に注目しておりました。
今回の公開飛行成功の知らせをうけ、十年以上に渡る八谷さんの偉業を讃えたいと思います。八谷さん、おめでとう!
 |
| これはおまけ。 |
http://www.petworks.co.jp/~hachiya/works/OpenSky.html